よく思われがちな印象

- お手伝いさん 家政婦
- お年寄りから言われたことなんでもする人
- お話し聞く人
- リハビリする人
- etc…
全く未経験の人は、色々あると思います。
ちなみにうちの父親は、家政婦と同じや!!と言ってました。
なかなか失礼ですね。(父親は当時僕がまだ介護の仕事をしていると知りませんでした)
と言う僕も、介護の研修(初任者研修)を受けるまでは「お年寄りから言われたことなんでもする人」=「お手伝いさん」って思ってました。
介護とは?

結論から言うと
高齢者や介護が必要な方の身の回りの世話をしたり、自立を支援することです。
寝たきりや介護が必要な方の排泄、食事、移乗等を介助する。
言われたを全てしてしまうと、本人の自立支援、リハビリにならないので、出来ることはできるだけ自身でして頂くよう促したり、声をかけるのも介護の仕事だと僕は思います。
介護の三大原則
介護には三大原則があります。
グーグル等調べればすぐに出てきますが、実際に働いでいると必死でこのことを忘れがちになることも多々。。。
まだまだです。
- 生活の継続性
- 自己決定の尊重
- 残存能力の活用
生活の継続性とは?
今まで生活を継続することです。
施設に入っても、介護が必要になっても、その人の生活を出来るだけ継続していこうと言う考えです。
確かに高齢者であれば、今までの長い生活があったのにいきなり生活をガラッと変えれてしまうと混乱しますよね。
あんまり生活環境を頻繁に変えたりすると、認知症を進行させてしまうような気がします。
うちの施設は、家に帰ったり、施設に入ったりを繰り返すことがあるのですが、
それを繰り返してるうちに混乱してしまい、元々あった認知症がひどくなってしまって
家なのか施設なのかわからなくなってしまうってことがありました。
自己決定の尊重
書いてる通り、本人の意思を尊重するです。
でも実際には、寝たきりでしゃべることが出来ない人とか、なかかな自分の意志を言えない人などはこちらで意思をくみ取るしかありません。
これが、他の介護士に聞いても、なかなか意見がバラバラで大変。。。
もちろんそう言う時は、家族さんの意見なども取り入れて、本人の意思を決定していったりします。
残存能力の活用
今ある能力を活用すると言うことです。
例えば、左上肢(主に左腕など)が麻痺の人でも、右上肢は動きますよね。
動く方もこのまま何もしなければ、いずれ固まってしまったり、動きが悪くなったりするので、その予防であったり、
逆に左上肢が、少しでも動くのであれば、左も使って頂いて少しでも動くようにリハビリをしていただく等
僕のところでは、本人の状態を確認して、動きにくい方も動かしてもらって可動域を増やし足り、日常的にリハビリを行ったりしてます。
実際のところ

実際のところなかなか三大原則が出来ていないことが、多いです。
と言うのも、職員が少なくてその余裕がない場面が多いとか。
例えば、ズボンの上げ下げをしてほしいが、職員が少なく見守りが出来ないため、ズボンの上げ下げをこちらでして早くしてしまう。
食事介助の人が多いので、本人が食べれるがこちらで食べさせてしまう等
大切なこと

新人の時、忘れがちなこと
実施には、出来ていないことが多いですが、何より大切なのは利用者さん中心で考えることです。
どうしても、新人の時などは、業務中心になってしまいます。
僕もそうでした。
少し慣れてくると周りが見えてきて、自分がいかに押し付けの介護をしていたのかと言うのがよくわかりました。
利用者さんも僕らと同じで、感情があります。
そのことは決して忘れてはいけません。
走り続けることも大事ですが、同じくらい立ち止まって周りを見ることも大事だと思いました。


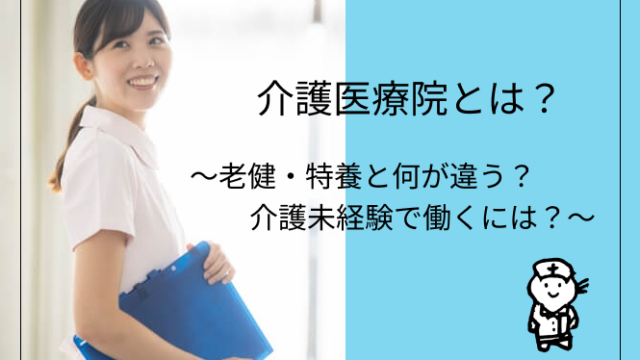
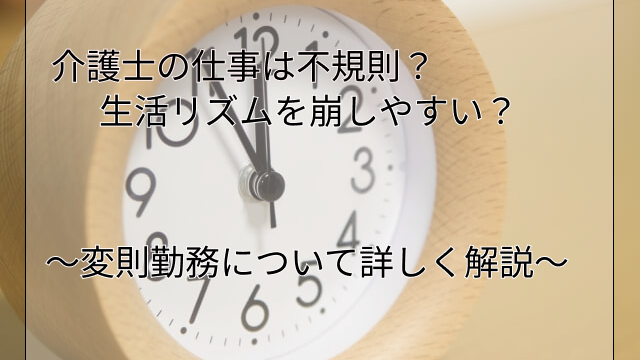


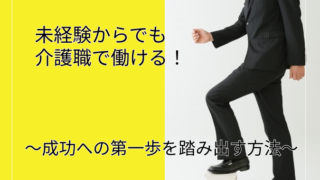
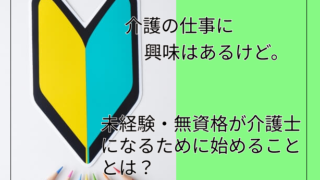
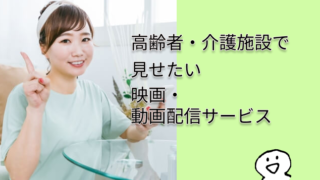
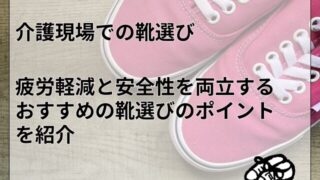
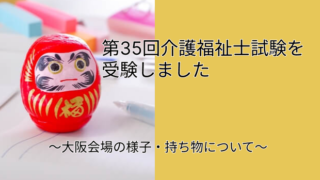
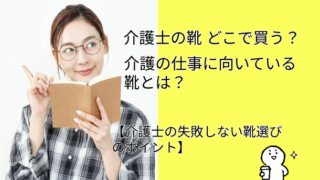
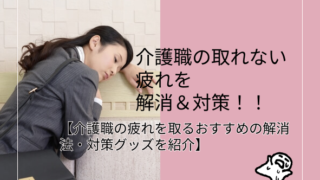



-300x169.png)