こんにちは。未経験介護士のcandy(@candy08989116)です。
僕のところは、今回で3回目の利用者さん隔離になりました。(令和3年12月現在)
今回はクラスターには、なりませんでした。
ですが、なぜ介護施設ではクラスターが起きやすいんでしょうか?
介護施設での新型コロナウィルスによるクラスター発生事例はよく聞きますね。
特に感染のピーク時には、かなりの施設が隔離をしているんではないでしょうか。
なぜクラスターが起きやすいのか、現役介護士の体験談を踏まえて紹介していきます。
クラスターの定義とは?

新型コロナの感染者集団=クラスターというイメージです。ですが、
クラスターは、現時点で、同一の場において、5人以上の感染者の接触歴等が明らかとなっていることを目安として記載しています。
厚生労働省 感染拡大防止と医療提供体制の整備 より
定義されています。
同一の場=介護施設
ということになります。介護施設で、5人以上の感染者が出れば、クラスターと認定と言うことになりますね。
そもそも新型コロナウィルスはどうして感染するのか?

新型コロナウィルスの感染は、
- 飛沫感染
- 接触感染
です。
咳、くしゃみ、つばなどにより感染します。そのための一番有効な手段はマスクと言われてますね。でもそれは、感染物を飛ばさないためで、ガードには弱いんです。目からもウィルスは侵入してきます。マスクも完全には、防ぐことが出来ません。マスクは何より他人に映さないために絶対にしておきたいものですね。
手にウィルスが付き、それをそのまま口や鼻を触ってしまった。時に感染します。よく手洗い消毒を言われているのもそのためです。ただ、手洗いも必ず石鹸を使用してください。流水だけでは、菌は死にません。自分を守るため。他人を守るためにも必ず手洗いをしてください。
新型コロナウィルスだけでなく、普段から手洗いをしていることで感染することを防ぐことが出来るんだ。インフルエンザも含めて!!
ワクチンは?
ワクチンも感染防止のために打ってくださいとよく言われますね。
ウィルスは目に見えません。それほどの効果があるのか正直疑問です。
ですが、インフルエンザでもワクチンを打つように、感染後の重症化は防ぐことが出来るはずです。
ただどれだけワクチンを打っても個人の免疫力が弱かったり、飛沫感染するような環境にいればかかります。
こればっかりは、個人の見解によるので、なんとも言えません。
なぜ介護施設では、クラスターが発生しやすいのか?

クラスターしやすい4条件
クラスターは4つの条件が揃ったときに、発生しやすいと言われています。
- 閉鎖された空間
- 距離が近い
- マスクをしていない
- 一定時間以上の会話
介護施設は、まさにこの4条件を満たした空間と言えます。
そのため、介護施設ではウィルスを入れないことが重要です。
介護施設はギリシア神話のトロイの木馬と似ているって僕は思ってました。
外には強いが、中に入ってしまうと一気に崩れてしまう…。
介護施設では、コロナ対策してないからクラスター起きるんじゃの!?
そんなことありません。しっかり対策をしています。
ただ、コロナウィルスは無症状もあるので、感染しているのか見極めがかなりむつかしいです。
施設でしているコロナ対策について

食事席は、各居室の人で固定している
コロナ発生前は、個人の相性等を考えて食事席を決めていましたが、1度クラスターしてからは、各居室の方と固定することになりました。
もし、ある利用者さんがコロナに感染しても、食事席と居室が同じであれば、接触する可能性が高いのは、同じ食事、居室の方のみに限定されます。
そうなると濃厚接触者を特定しやすく、感染者も少なくすることが出来ます。
食事席には、パーテーションをしている
これは一般の食事処に行くとしているように、パーテーションを食事席でしています。
出来るだけ、ウィルスを移さないようにするためです。
利用者さんにも可能な限りマスク着用を
お互いに移らない移さないためにも、出来るだけマスクの着用をお願いしています。
ただ、普段からマスク着用の癖がない方や、理解力によりマスクをしない。すぐに外してしまう方も中にはいます。その方には、何度も職員から声かけやマスクをするようにしています。
職員も常にマスク+フェイスシールド+手袋+毎日の検温
コロナウィルスは、内部で勝手に発生しません。
ウィルスを持ち込んで来るのは、職員か家族さんになります。
そのため、職員では、必ず
- マスク
- フェイスシールド
- 手袋
- 毎日の検温
が義務化されています。
施設によれば、定期的に抗原検査があるところも
もちろん入浴介助時もマスク+フェイスシールド+手袋着用です。
使いまわしのもの使った際には、必ず手指消毒
レクリエーションなどで各利用者さんが使いまわしのものを使用した際には、必ず手指消毒をしています。
職員の休憩も同じ部屋で過ごさないように
これも職員間でお互いに映さないためです。
食事をとる際には、別々の部屋や広い部屋で間隔を開けてとるようにしています。
家族さんとの面会はコロナの世間の感染レベルにより、リモートあるいは面会なしに
これは施設によって、判断基準が違います。
僕のところは世間のコロナの感染者数(県内の感染者数が、500名以上)になった時に、面会を対面からリモートに切り替えたり、隔離時には完全に面会禁止になったりします。
ここまで感染対策しているのに、なぜクラスターが起きるのか?

介助する際に、職員と利用者さんの距離が近い
密接にかかわるため、普通にマスクをしているだけでも感染のリスクが高まります。
一般の人が普通に会話する距離よりも、耳が遠いこともあるので、かなり密になって会話したりするからです。
無症状な人がいるため、わかりにくい
症状が全くでない人いるので、コロナに感染しているとわからずに仕事に来ている方も中にはいるはずです。
また利用者さん同士でも無症状同士であれば、全く感染に気づかずに会話をしている可能性もあります。
それから、たまたま有症状の方がいて、初めてコロナ感染者がかなりいたとわかることもあります。
換気もしているが、高齢者は寒がりが多い
少し風が拭いただけでも、寒いという方がいます。
それはたとえ暖房であっても寒いと感じてしまうほどです。
そのため、換気のために窓を開けていてもいつの間にか閉まっていたということもあります。
安全のために窓をあけることが出来ない
また、認知症の方が多い施設では、窓から飛び降りてしまう可能性もあります。
窓をそもそも開けることが出来ないところも中にはあります。
病院で入院出来ないときは、施設で診る必要がある
病院が逼迫していれば、たとえ重症者でも受け入れをしてもらえないこともあります。
そのため、介護施設で重症者を診ることになり、職員が感染してしまい、他の利用者さんへと感染が移ることもあります。
利用者さんの理解力次第で、感染が広まることもある
何度説明しても部屋からどうしても出てしまう方や、その間に陽性者が他の部屋に入ってしまう時も。
また、利用者さんが暴れたり、帰宅願望等の不穏になった際に、話の傾聴を行うとどうしても時間がかかってしまいます。
そうなると、職員、利用者さんのどちらかが陽性であれば、感染が広まってしまうこともあります。どんなに職員が気をつけていても、いつの間にか広まっていることもあります。
慢性的な人手不足により、軽症ならと出勤してしまうことも
人員が足りない関係で、少しくらい喉が痛くてもと思って出勤すれば、実は陽性でしたとい言うこともあります。
ギリギリの人員で回しているところだと、コロナ陽性のことが、頭によぎっても休みにくいというのがどうしても頭をよぎってしまします。
どうすればよいのか?
休みやすい雰囲気を作る
コロナを持ってくるのは、外部と接触のある職員か家族さんです。
家族さんは、面会がリモートになっていれば、直接会うことはないですが、職員は直接利用者さんと接します。
職員が何か少しでも異常があれば、休むこと。
休みやすい雰囲気があることが一番です。
そのためには、もちろん人員の余裕があることも必要ですが、何より日ごろからその雰囲気を作っていることが大事です。
中には、家族の人が陽性で着替えの衣類にウィルスが付いている場合もあるかもしれない…。
手洗いを常に心がける
職員は1ケア1手洗い。
利用者さんもトイレのあとや食事の前にはしっかりと手洗いをしてもらうことが需要です。
手洗いが出来なくても、手指消毒は出来るはずです。感染を少しでも抑えることが重要です。
換気をする・マスクもできるだけ着用していただく
多少寒くても換気をしっかりとする必要があります。
寒いと訴えがあれば、しっかりと衣類を着てもらいましょう。
菌がとどまれば、それだけで感染のリスクが広がります。
おわりに
なぜ介護施設では、クラスターが起こりやすいかわかったでしょうか。
世間では、withコロナ と言われていますが、介護施設では正直かなりむつかしいです…。
もうかれこれ3年は、家族さんがフロアに上がってきていません。
1日でも早く以前の生活に戻れることを切に願います。



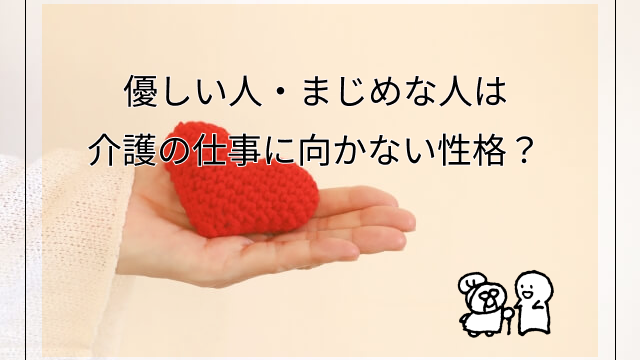
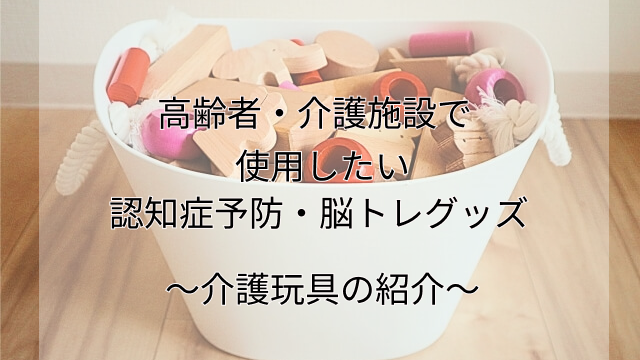
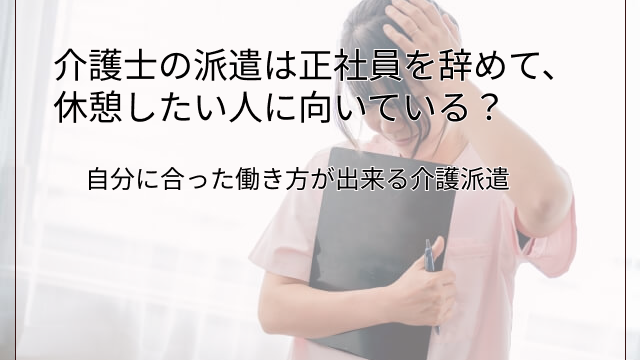
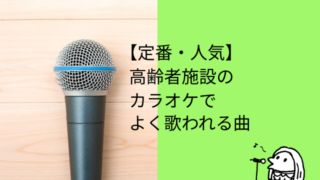

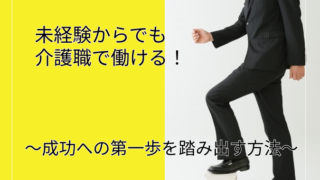
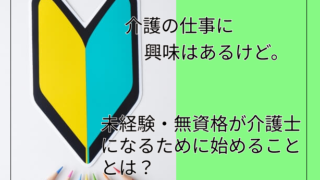
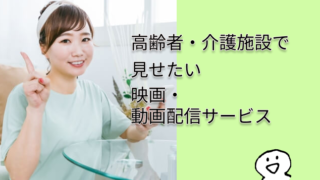
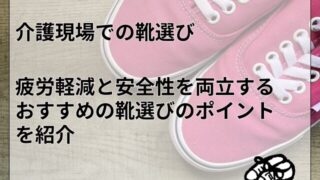
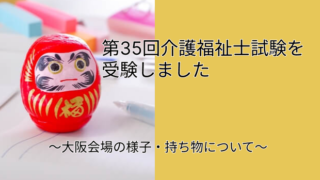
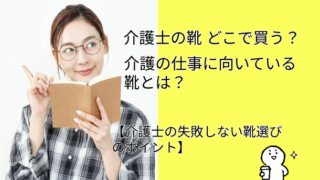
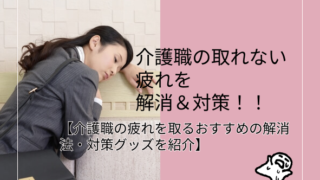



-300x169.png)